大阪府在住、男子二児の母です。
ご訪問ありがとうございます。
現在小学四年生の、ASD(自閉症スペクトラム)とADHDの診断を受けた
長男の成長記録のブログです。
阪神タイガースが大好きな父ちゃんによる野球話もよろしくお願いします。
また今日も始まってしまった…
そう感じるのは、公文の宿題タイム。
ADHD傾向のある長男と机を挟んで向かい合うと、空気がピリッと張りつめます。
宿題中、バトル発生の瞬間
同じプリントを3回目に取り組んでいた日のこと。

公式、もう覚えた?
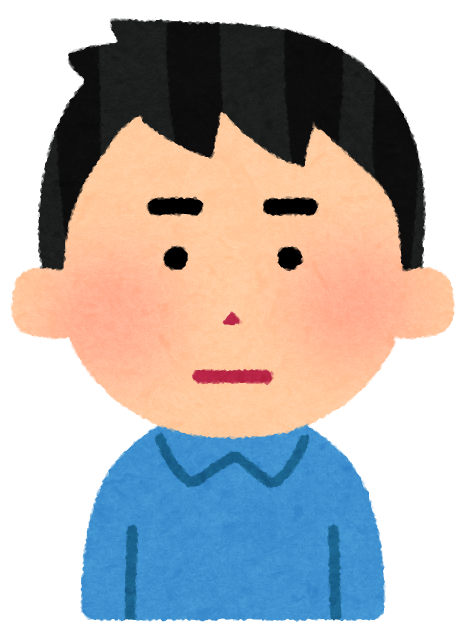
覚えない

いやいや、覚えへんかったら解けへんやん。声に出して3回言ってみ?

3回で覚えられるわけないやろ

3回が大事なんちゃうねん。本筋そらさんといて。3回でムリなら5回言ってみたらええやん
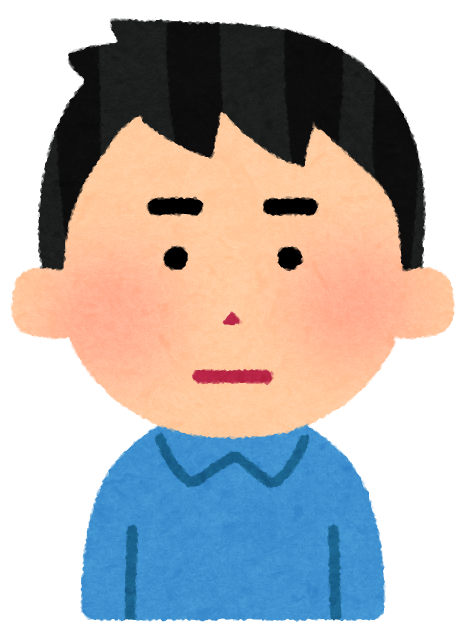
でも覚えられへんねん…(←口に出して覚えるのをしたくないのでしない)

“覚えない”って言い切るなや〜
……結果、沈黙。母、軽く沈没。
「覚える気がない」のか、「覚えられない」のか
発達障害のある子どもにとって、“覚える”という行為そのものが大きなハードルになることがあります。
「覚えたいのに頭に残らない」「同じことをしても次の日には忘れてしまう」
そんな本人なりのもどかしさが、確かにあるんです。
でも、親の立場から見れば「公式を覚えたらすぐ解けるのに」と思ってしまう。
それが、親子のすれ違いを生むんですよね。
一見、“覚える気がない”ように見えて、実は「覚え方」や「理解の仕方」がその子に合っていないだけというケースも多いです。
頭ではわかっているんです。
でも、つい感情が先走ってしまう。
そしてつい言ってしまうんです。
「そんなに覚えるのイヤなんやったら、公文もうやめたら?」って。
言ったあと、毎回「また言うてもうた…」と自己嫌悪。
でも、そう簡単に冷静ではいられないのが、家庭学習のリアルなんですよね。
集中力が続かない、読まずに解く、席を立つ…
算数の内容が難しくなってきたこともあり、集中力はどんどん落ちてきています。
問題文を読まずに解きはじめたり、途中で急に席を立ったり。
母は「せめて一問終わってから立って」と1000回くらい言いましたが、なかなか届かず。
途中で離席して戻ると、どこまで解いたか確認せず次に進んでしまう。
結果、答えが出ていないのに次の問題へ突入するという、よくあるパターン。
見るだけで途中と分かるはずなのに、本人はスルー。
これは単なる集中力の問題ではなく、“確認”の苦手さが関係しているのかもしれません。
字の読みづらさも地味にハードル
長男のノートを見ていると、字がなぐり書きで読めないこともしばしば。
「x」と「()」の区別がつきにくく、「a」と「9」もそっくり。
自分でも何を書いたか分からなくなって、答え合わせができないという悪循環。
これも学習の進みづらさに拍車をかけています。
公文の“繰り返し学習”でも改善しにくい壁
公文の良さは、同じプリントを何度も繰り返すこと。
でも、長男の場合、5回やっても間違える場所が同じ。
理解できていないのか、忘れてしまうのか。
努力が結果につながらない日々に、母も少し不安になります。
「これで本当に力になってるのかな…」と。
それでも「続けたい」と言う理由
母としては、「覚えない」「読まない」「途中で立つ」この三拍子で正直ヘトヘト。
でも、長男は「公文はやめたくない」と言い張ります。
おそらく、本人にとって公文は“安心できる場所”なんだと思います。
友だちがいる環境で、先生にやさしく見てもらえる安心感。
それが続けたい理由なのかもしれません。
母の学び:完璧じゃなくても、続ける意味がある
「覚えないならやめたら?」とつい言ってしまうけど、心のどこかでは「やめさせたくない」と思っている自分がいます。
発達障害の子の勉強は、“結果”より“過程”が大事。
今日も机に向かっただけで、十分すごい。
そう思えるようになるまで、母も修行中です。

今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
みなさんの応援が力になります!



コメント