大阪府在住、男子二児の母です。
ご訪問ありがとうございます。
現在小学四年生の、ASD(自閉症スペクトラム)とADHDの診断を受けた
長男の成長記録のブログです。
阪神タイガースが大好きな父ちゃんによる野球話もよろしくお願いします。
はじめに:就学前に直面した“最初の大きな壁”
小学校入学を控えた時期、発達特性のあるお子さんを持つ家庭では、
「通常級にするか」「支援級にするか」という大きな選択に直面します。
わが家の長男もそのひとり。
特定の刺激に敏感で、集団の中では緊張しやすく、気持ちの切り替えが少し苦手。
小学校という新しい環境で、どう過ごせるかは正直、未知数でした。
この時期、教育相談や学校見学を何度も繰り返し、先生方にもたくさん話を聞きました。
それでも「どちらが正解か」は誰にもわかりません。
最終的に、私たちは通常級でのスタートを選びました。
ここでは、そのときの悩み、決断の理由、そして入学後に感じたことをまとめています。
これから同じ悩みに向き合う保護者の方の参考になればうれしいです。
支援級の見学で感じた「安心」と「不安」
就学前に、支援級(特別支援学級)の話もお伺いしました。
教室は静かで、環境は整っていて、先生が丁寧に一人ひとりと向き合ってくれる。
“安心して学べる空間”という印象が強かったです。
ただ、その一方で少し気になる点もありました。
最近は支援級を希望する児童が増えていて、「この人数で十分な支援が行き届くのだろうか?」という現実的な疑問が残りました。
もちろん、先生方は一生懸命サポートしてくださいます。
けれど、制度としても学校としても、リソースには限界があります。
サポートの質が子どもによってばらついてしまう可能性も感じました。
子どもの「気持ち」を大切にしたいという想い
一番大きな決め手は、本人の気持ちでした。
長男は、「友だちと同じクラスで勉強したい」とはっきり口にしていました。
支援級に入ることで安心できる部分もあるかもしれません。
でも、「本人の望む環境でスタートを切ること」は、彼にとっての“自己肯定感”につながると思ったのです。
もちろん、挑戦の場を選ぶということは、同時に“困難”も増えるということ。
それでも、「まずはやってみる」ことを選びました。
通常級を選んだ現実:最初の1年間で見えたこと
入学後の生活は、やはり一筋縄ではいきませんでした。
集団行動では遅れが出ることもあれば、集中が切れて授業中に無の境地になっていたこともありました。
周囲の目が気になる場面も多く、私も何度も胸が締めつけられる思いをしました。
それでも、幸いだったのは担任の先生の理解。
「完璧にこなすことよりも、まず“できた瞬間”を大切にしてあげましょう」と言ってくださり、家庭と学校が連携して支える形をつくることができました。
学校全体のサポート体制が支えに(保育所等訪問支援を活用)
通常級を選んだとはいえ、家庭だけで支えるのはなかなか難しいもの。
そこで私たちは、保育所等訪問支援を小学校入学前から利用していました。
この支援は、専門の支援員さんが保育園や学校などを訪問し、子どもが集団生活の中で安心して過ごせるよう、環境づくりや先生への助言をしてくれる制度です。
長男の場合も、入学当初に支援員さんが学校を訪れてくれて、「こういう場面で不安が出やすいです」「こう声をかけると落ち着きます」といった“本人に合ったサポートの仕方”を先生に伝えてくださいました。
そのおかげで、学校側も長男の特性を理解しやすくなり、少しずつクラスに馴染めるようになっていきました。
家庭・学校・支援機関がつながると、「どこでつまずきやすいのか」「どう助ければいいのか」が共有され、本人の安心にも直結します。
支援の形は人それぞれですが、こうした連携があることで、“通常級でも安心して過ごせる道”が少しずつ見えてきた気がします。
家庭での支援の工夫:小さな積み重ねが大きな力に
家庭でも、“見通しのつくサポート”を意識しました。
こうした小さな積み重ねは、学校での落ち着きにもつながりました。
発達特性のある子どもは、「何をすればいいのか」が明確だと安心できます。
家庭でその環境を整えることは、通常級で頑張るための“土台づくり”になると思います。
支援級・通常級のメリットと課題を整理してみた
ここで一度、私自身が感じた両者の特徴をまとめておきます。
| 観点 | 支援級 | 通常級 |
|---|---|---|
| 環境の静けさ | 落ち着いて学べる | 集団の中では刺激が多い |
| 教師の目の届きやすさ | 一人ひとりを見てもらえる | 先生は全体を見て動く必要あり |
| 友だちとの関わり | 少人数で深く関わりやすい | 幅広い人間関係を経験できる |
| 本人の満足感 | 安心感を得やすい | 同年代と「同じことができた」経験が自信に |
| 学習進度 | 個別に調整可能 | 学年全体のペースに合わせる必要あり |
どちらにも“良さ”と“難しさ”があります。
大切なのは、「その子にとって今どんな環境が必要か」を冷静に見つめることです。
就学相談の時の説明で感じた“空気の違い”
就学相談の時に先生からお伺いした話。
1年生のうちは、支援級は比較的静かな環境。
通常級は少しざわついているときもあるし、テンション高めの子もいたりする。
椅子に45分間座り続けるのも最初は難しい子もいる。
そのとき、ふと思ったんです。
「この“にぎやかさ”の中で生きる練習も、長男には必要なんじゃないかな」
静かな環境は確かに安心です。
でも、将来的に社会に出たとき、周囲はいつも穏やかとは限りません。
だからこそ、少しずつ“多様な人の中での生き方”を学んでほしい。
それも、通常級を選んだ理由のひとつでした。
学年が上がるにつれて見えてきた“成長”
小学校4年生になった今、長男はまだ課題も多いですが、明らかに“成長したな”と感じる場面が増えました。
苦手だった集団行動も、少しずつ自分なりに対応できるように。
一番大きいのは、「助けを求める力」がついたこと。
少しずつではありますが、困ったときに「先生、今これわからない」と言えるようになったんです。
これは、通常級という環境の中でたくさんの試行錯誤を繰り返した結果だと思います。
支援級・通常級の選択に「正解」はない
このテーマに、絶対的な正解はありません。
子どもによっても、学年や時期によっても、最適な環境は変わります。
支援級を選ぶのも勇気。
通常級で挑戦するのも勇気。
どちらを選んでも、その選択が“そのときのベスト”であれば、子どもはちゃんと成長していけると、今の私は信じています。
まとめ:選んだあとの“伴走”が一番大事
支援級か通常級か——。
この選択はスタート地点にすぎません。
どちらを選んでも、親ができることは「見守り」「理解し」「支えること」。
そして、子どもの変化に応じて柔軟に環境を見直していくことです。
私は今でも、「もし合わなくなったら、そのときまた考えよう」と思っています。
大切なのは、子どもの安心と成長が両立できる環境を探し続けること。
これからも悩みながら、一緒に歩いていこうと思います。
※本コンテンツには広告(PR)を含みます
📚 おすすめ就学サポートアイテム
応援クリックしてもらえると、更新の励みになります!
母ちゃん、今日もがんばれます。
長男のことや家族のエピソードを、もうちょい深掘りして書いてます。
のぞいてもらえると、めっちゃうれしいです。


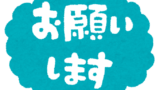


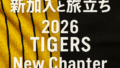
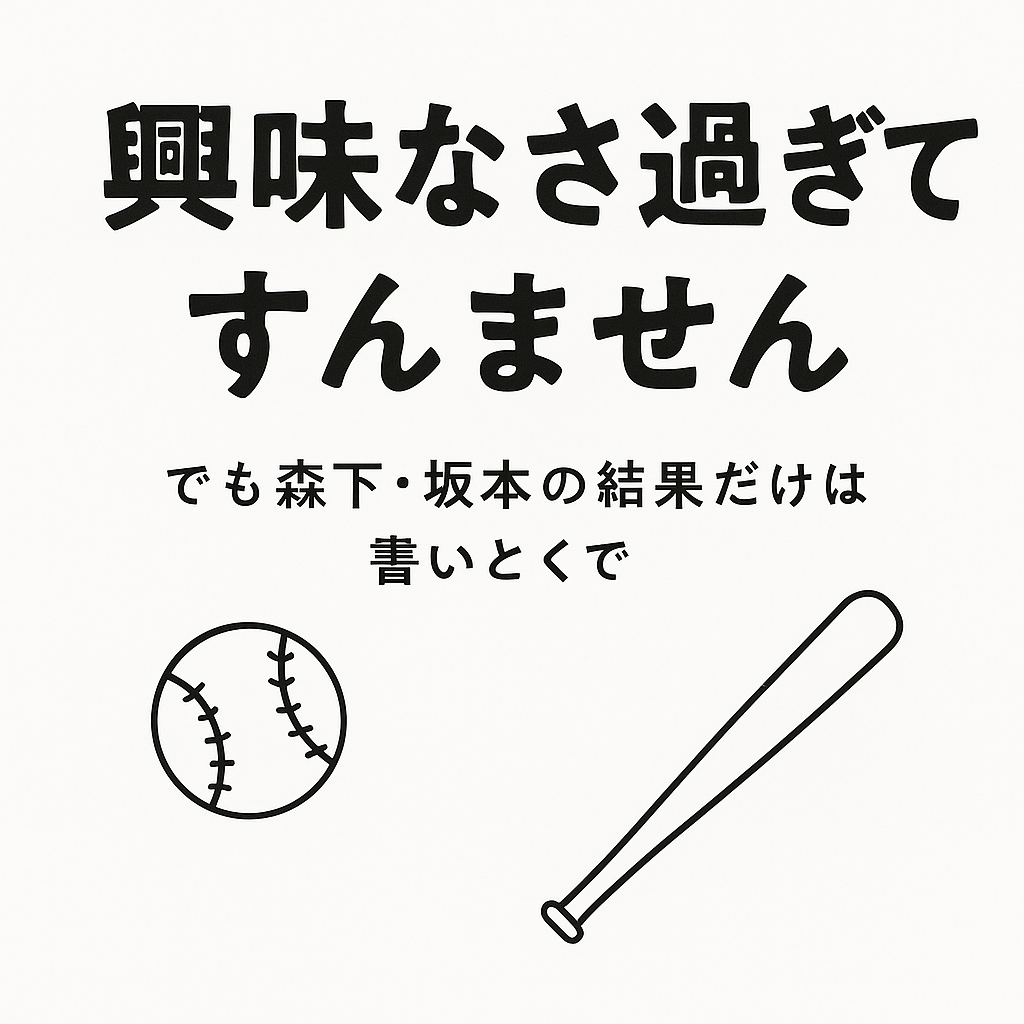
コメント